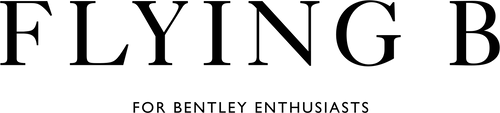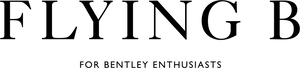Bentley DNA
Bentley 4 1/2 Litre Vanden Plas
ユノディエールの陽炎
ベントレーの歴史を語るとき、ル・マン24時間レースを席巻した栄光のヴィンテージ期を抜きにして語ることはできない。メイクスの格と、積み重ねてきた歴史のおおもとが、今なおそこに厳然と存在しているからである。
強大なトルクをもって突進するベントレー4 1/2リッター・ヴァンデンプラス。
齢80を越えるオールドレーサーのレーシングスクリーンを通して観る地平線には、今なお過日の陽炎が揺らめいている。
text: 吉田拓生
photo: 田中秀宣
cooperation: 永遠ボディー
cooperation: Rustic Gold

格闘の図式
英国随一のハイスピード・トラックであるスラクストン・サーキットのスターティング・グリッドでフォーメーション・ラップのスタートを待っている時、我々の頭上で急激に発達した雨雲から雨が溢れ出した。一時はコース脇の赤いシグナルすら見えないほどの強い降りとなり、コース上はカメラマンの踝が水に漬かるほどになっていた。てっきりレースが延期になると思い込んだ私はレーシング・エンジンの昂ぶりを鎮めるために右足でブリッピングするのをやめた。ところがその直後シグナルが無情にもグリーンに変わり、レースカーたちは少しの迷いもなく池のようになったコースに引き波を立てて漕ぎ出していった。一瞬で喉が渇ききり、息を呑もうとして盛大にむせてしまった。「これはクルマのドライブというより格闘だぞ」と自分に言い聞かせ、下腹にありったけの力を込めたことを、今でもはっきりと思い出すことができる。
そう、今からはじまるドライブの舞台は快晴の一般公道だが、しかしこれも格闘に違いない。往年のル・マンカーと同じヴァンデンプラ製のスポーティで軽量なファブリック・ボディを纏った漆黒のベントレー4 1/2リッター。このクルマのホイールベースはコンチネンタル・フライングスパーよりもさらに2センチほど長く、しかし車幅は5ナンバー枠にぴったり収まるほど狭いという細長さによって、まるで鋼鉄の塊から削り出した機関車のような迫力を湛えている。W.O.ベントレーが元々蒸気機関車のエンジニアだったという来歴がそう思わせるのかもしれないが、このW.O.は器用に曲がったり止まったりすることより、もっぱら突進し続ける不退転の決意のようなものを全身に漲らせているのである。
メカニックシート(そう、助手席とは呼ばない)を跨いでドライバーズシートに収まり、冷たいシフトレバーを握ると、かつてのスラクストンでの記憶が甦り、全身に鳥肌が立つのがわかった。戦前に生産されたいわゆる"ヴィンテージカー"をドライブした経験は片手以上あり、その中にはレーサーも含まれるのだが、そんな私でもベントレーほどの大物ははじめてである。現代のクルマと違い、ヴィンテージカーの操作系の重さは車体の大きさに比例する。5.25幅のタイヤというのは、現代の基準に置き換えればハイエンド・スポーツカーが履く200番台後半のタイヤ幅に等しい。それをパワーアシストなしで扱うのだから、上半身の格闘の様が想像できるのではないだろうか。
一方、下半身の課題は上半身のそれを軽く凌駕する。この時代のベントレーは、ペダルの順番に特徴があるのだ。右からABCではなくBAC、想像できるだろか? センターマウント・スロットルという名称のとおり、スロットルペダルが真ん中に据えられているのである。オーナーの要望によって一般的なABCに変更されてしまった個体も中にはあるようだが、真のヴィンテージ・ベントレー遣いならば、車体ではなく自らの常識を改造すべきだろう。右足でブレーキとスロットルの位置を探り、その感触を確かめる。もしシフトダウンを敢行するならば、ヒール・トゥではなくトゥ・ヒールにしなければならないのだろうか? 下半身というより、これはもう頭の体操である。それも、失敗したら取り返しがつかない頭の体操。かつてドライブしたF1マシーンの場合、上半身はマッチョなプロレスラー、下半身は引き締ったバレエダンサーを意識する必要があったのだが、今回はドライビング・ポジションががっちりと固定されない分、下半身にも相応の力が必要になるだろう。覚悟は依然として曖昧なままだが、しかし格闘ははじまる。

4気筒の暴走機関車
マグネトー等のスイッチ類をひと通りonにしてから、スピードメーターとレヴカウンターに挟まれたスターターボタンを押し込む。機械的なノイズが一斉に高まり、エンジンに火が入った。エグゾースト系が完全なストレートスルーではないため、ボリュームは思っていたよりも控え目だった。そのかわりにドライバーはマグネシウム鋳物のバルクヘッドの隙間から溢れ出すエンジン腰上の打鍵音に包まれることになる。ベントレーのパワーユニット、それも4.4ℓもの排気量があるにも関わらず気筒数がたったの4本しかないという事実は少し奇異に思われるかもしれない。現代の常識ならば、排気量やブランドの格からしても、6〜8気筒以上のいわゆるマルチシリンダーを想像してしまうものである。しかし、今から82年前の創造物にモダンな常識は通用しない。おまけに、オーバーヘッドに配されたカムシャフトが1本であるにも関わらず、気筒あたり4バルブを備えるあたりも珍しい。
屈強なラダーフレームを通してコックピットに伝わってくる振動は"82年前の4気筒エンジン"というスペック通りの豪快なものだが、一方センターマウントのスロットルペダルは妙にストロークがスイッチのように短く、全ての回転域でエンジンを上手に扱いきれる自信が到底涌いてこない。
前進4段、後進1段のギアボックスは、シンクロ機構を持たない。イギリス、ヒューランド社の製品に代表されるような、いわゆるレーシング専用のギアボックスも「シンクロがない」と表現されることがあるがそれは間違いである。一般車のようなシンクロメッシュのかわりにギア同士の同調を瞬時に促すドグリングと呼ばれる機構が付いているのだ。それに対しヴィンテージ・ベントレーはまさに裸のギア同士がぶつかり合うダイレクト・シフトである。このため回転の合わせようがないファーストギアにエンゲージする瞬間は、シフトレバーを通してけっこうな衝撃が伝わってくる。だがこれもヒストリックカーの定石通りシフトレバーで2速の入り口を舐めてから素早く1速にシフトする方法でトライすると、いくぶん滑らかにエンゲージされることがわかった。
クラッチは近代的なダイアフラム・スプリングがまだ存在しない時代のシロモノであり、当然のように繋がりは唐突だ。それでも今回1度もエンジンをストールしなかったのは、恐ろしくトルクフルなベントレー4 1/2リッターのおかげである。むしろ問題なのはトルクがあり過ぎることであり、ブレーキ・ペダルを踏んづけたくらいではエンジン・ストールさせることはできず、乗り手の意に反してグイグイと前進していこうとすることである。その様は、まさに意志を持った暴走機関車の如しであり、これまで感じたことのない恐怖感に襲われる。
トルクフルなエンジンに合わせて設定された4段のギア・レシオは心許ないくらいに高いので、レヴカウンターのフルスケールが4000r.p.m.までしか振られていなくても、そして実際に2000r.p.m.に満たない回転域で走らせていても、スピードの乗りはすこぶる良い。タイヤが転がりはじめるとステアリングの重さは半減されるが、それでも片手ハンドルなどもっての他であり、コーナリング中のシフトは慣れを要する。2速以降のシフトはダブルクラッチを併用したり、様々な方法やタイミングを試してみたのだが、どうやら2500r.p.m.以上までエンジンを引っ張って、その後迷うことなく、大いなる決意とともにゲートに叩き込むことが最良の策であるように思えた。ガリッと音がするときもあれば、スッとキレイに呑み込んでくれることもある。こればっかりはチョイ乗りで習得できるような技術ではない。オーナーのみが窮められる深淵であろう。


レーシングスクリーンの先に見えるもの
体を包み込むノイズ、神経を麻痺させるようなバイブレーション、ドライビングハイへ誘う混合気の臭い、水門のバルブのように重たいステアリング、そして暴走機関車並みのトルク、そしてありったけの緊張をともなうギアシフト。ヴィンテージ・ベントレー特有のファースト・インパクトは、やはり一般的なクルマのドライブとはまるで勝手が違う。それだけに、漆黒の巨体が自分の意の通りに滑りはじめたときの感動は筆舌し難いし、まさに高尚な自動車史の1ページに自分が刷り込まれたような、そんな充足感すら感じられるのだ。
ひと通りのファースト・インパクトを乗り越えた後、コックピットで背筋をピンと伸ばして深呼吸をして、ひと通りの感情を整理すると、これまで閉ざされていた重々しい扉が、目の前で開かれる。そこにあるのはNVH(ノイズ、バイブレーション、ハーシュネス)を除いた純粋なヴィンテージ・ベントレーのキャラクター、ドライビング・フィールである。
ここまでの豪快でどちらかといえば大味なイメージとは裏腹なほど、ベントレー4 1/2リッターが突き進む際の路面へのタッチは繊細なのである。振動は盛大なのだがしかし数多ある軸受けには不自然なガタが感じられず、また時とともに反力を失うこともあるリーフ・スプリングは今なおしなやかに振動をいなしており、ロードホールディングに貢献している。ストロークの極端に短いスロットルペダルと、意外にもレスポンスの鋭いエンジンの組み合わせも、乗り手の気持ちが攻撃的に転じられれば充分に扱いやすい範疇にある。モダンな物差しをかざしてみれば、加速こそ驚異的だが、しかしコーナーでは見た目通りに重々しく、制動力はボディ外側にレバーの生えたハンドブレーキで補ってもなお貧弱であることは認めるしかない。それでもヴィンテージ・ベントレーが時代をはるかに超越した精度で組み上げられていることはひしひしと伝わってくるし、その挙動は信用に足る。80年の時を遡れば、このクルマが自動車技術の頂点に君臨していた事実は歴史が証明している通りなのだ。
このベントレーの頭抜けたポテンシャルは、ル・マンのようなレースに勝つために蓄積されたものではなく、W.O.がエンジニアとしての理想を追求した結果、自然と身に付いたものであるに違いない。数々の国際耐久レースにおける勝利は、頂点を窮めた者が当然手にする副産物に過ぎなかったのだろう。タイヤが4つ付いているという共通点こそあれ、他のメイクスとは比べるスケールがそもそも違っている。そんな現行モデルにも通じる偉大なるベントレーのDNAは、4 1/2リッターのようなヴィンテージ期のモデルに根ざしているのである。
小さなレーシングスクリーン越しに広がっているのは、植物の緑と土の茶色が入り混じった陽炎のような地平線である。かつてこの暴走機関車を勇猛果敢に手なずけたベントレー・ボーイズたちも、ユノディエールの先に同じ陽炎を見ていたのだろうか。

1928 BENTLEY 4 1/2 LITRE Vanden plasとは
1919年の創業から1932年までに生産されたベントレーは、創業者であるW.O.ベントレー自身が開発に関わったこともあり、今なお特別な尊敬を集めている。当時の自動車メーカーはおもにシャシーとエンジンの製作を手掛けており、ボディはコーチビルダーと呼ばれる専門業者が架装していた。今回の取材車、シャシー&エンジン№ HF3195、レジストレーション№ YV1471は元々ヴァンデンプラス製のサルーン・ボディを纏っていたが、後年ル・マン・タイプのファブリック・ボディに換装されたヒストリーを持っている。

ル・マンカーはアルミ磨きのダッシュにブラックベゼルのメーターという組み合わせが多いが、取材車はウォルナットパネル+ゴールドリングのメーターが奢られる。ステアリングはスプリング・スポーク式が備わる。

ステアリングの中央にはホーンボタンではなく、ハンドスロットルと点火時期調整が備わる。ハンドスロットルは現代で言うところのクルーズコントロールのような役目を果たしていた。

ステアリングポストの右脇にはいかにもヴィンテージカーらしいスイッチパネルが配される。上はダイナモ、中段のノブは燃料のミクスチャー調整、そして下段はマグネトーのスイッチである。

ベントレーが創業時より革新的なメーカーであったことを現すパテント・プレート。特にスピードの出るモデルだけに、ブレーキ関係には特に独創的なアイデアが詰まっていたようだ。

前後長からストレート6エンジンに見えてしまう4.4ℓ 4気筒エンジン。前端のバーティカル・シャフトによってオーバーヘッドのバルブトレーンを駆動するシステムが特徴的。アルミやマグネシウムがふんだんに使われた眺めはストイックにして豪奢。

マグネシウム鋳物で作られたバルクヘッドはベントレー・シャシーの中核を成す構造部品。リビルドの際にリプロダクションされたアルミ製に替えられてしまっている個体もあるという。

ウォーム&セクター式のステアリング系統は車格に比例しかなりゴツい作りになっている。操作系の重さも相応だが、その作動感は非常に正確であり、直進性はすこぶる良い。

エンジン脇に備わるオイルキャップにはBの文字が繰り抜かれている。また穴が開いていることで腰下の圧抜きにもなっている。キャップを開けると茶漉しのような金網が仕込まれていてオイルの逆流を防いでいる。

ドアの内張りに浮き上がったBの文字。ブランドネームを示す意匠はあまり多くはないが、内張りの中に木で形作ったエンブレムを仕込むのは定番のモディファイといえる。

エンジンとシャシーが同じ番号のいわゆるナンバーマッチングは優れた固体の条件とも言われる。こちらはエンジンに刻まれたHF3195の打刻。

※『フライングB No.004』(2010年刊)に掲載された記事に加筆修正しました。掲載された情報は刊行当時のものです。