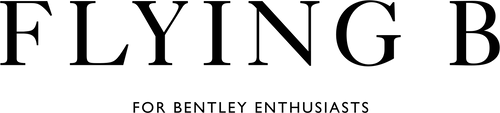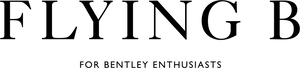THE END OF AN ERA
Mulsanne Speed
THE END OF AN ERA
Mulsanne Speed
フラッグシップ––ブランドのラインナップを連合艦隊に置き換え、 その旗艦となるべきモデルのことを、そう言い表すことがある。半世紀に渡り生き延びた伝統のエンジンを積み、400時間に及ぶ製造時間の大部分をインテリアに注ぎ込むという、比類なきクラフトマンシップに支えられたベントレー・ミュルザンヌは、まさにその称号にふさわしい1台だった。
words: Yoshio Fujiwara
photography: Kentaro Yamada
translation: Sarka Fenclova


「おわりと、はじまり」
まるで周囲の空気をも清めるかのように静かに佇む、この荘厳かつ、雅やかなサルーンを前にして浮かんだのは、そんな言葉だった。世界中から多くの惜別の声が寄せられる中、クルーで最後のミュルザンヌがラインオフしたのは、2020年6月25日のこと。
その瞬間、1959年登場のS2サルーンに搭載されて以降、連綿と改良が施されながら、フラッグシップ・モデルの心臓部としての重責を担ってきたV型8気筒OHV2バルブ・ユニットは、ついにその長い生涯に終止符を打つことになった。それはまたすべてがイギリスで設計、開発、製造される“ピュア”ベントレーが終焉したことも意味していた......。しかしながらそれはW.O.の時代から続くベントレーの精神の断絶を意味するものではない。むしろ、その逆だ。
2009年のペブルビーチ・コンクール・デレガンスで、1929年登場の8リッターと並べてワールドプレミアされたことに象徴されるように、2灯の大径丸型ヘッドランプはW.O.時代の継承であり、またブルックランズを彷彿とさせるグリーンハウスの薄いクーペライクなシルエットは、フラッグシップ・サルーンといえど、ミュルザンヌが生粋のドライバーズカーであることを高らかに宣言していた。
加えてミュルザンヌから導入された、アルミパネルを500度に加熱し、空気圧をかけて整形するスーパーフォーミング工法によって作り上げられたボディパネルは、同時に鋭いエッジと滑らかな曲面を描き出し、ヘッドランプなどの意匠とともに現代のベントレーへと繋がるデザイン・アイコンとしても重要な意味をもつモデルとなったのである。
一方メカニズム面においても、伝統の6.75リッターV8OHVにはツインターボ、可変バルブタイミング、気筒休止システムなど最新の技術をインストール。現代の環境基準に対応しながらも、スタンダードで512ps、ハイパフォーマンス版のミュルザンヌ・スピードに至っては537psを発生。スピードは、ZF製の8速ATを介して0-100km/h加速4.9秒、最高速度305km/hとスーパーカー顔負けのパフォーマンスを誇るに至った。
またシャシーにおいても、可変制御ダンパーを備えたエアサスペンションとステアリングを状況に応じて適切に制御するDCC(ダイナミック・シャシー・コントロール)を採用。全長5575mmという巨体を感じさせないドライバーズカーにふさわしい、ナチュラルでスムーズなハンドリングを実現している。
いま改めてミュルザンヌ・スピードに乗ると、精緻なクロノグラフのごとく、すべてのパーツが寸分の狂いもなくカッチリと組み合って動いているかのような古式ゆかしいアナログ感覚と、2.8トンの車重と537psのパワーを見事に手懐けるデジタル・デバイスとの調和ぶりに舌を巻く。
車内は驚くほど静かなのだが、アクセラレーターの動きに合わせて響くV8エンジンのサウンドと、ステアリングから感じるインフォメーションは驚くほど饒舌で、自動車を操る悦びに満ちている。
もちろん、上質なレザーとウッドを惜しげもなく使い、1つ、1つ丁寧に仕立てられたハンドメイドのインテリアは、色褪せるどころか、時を経るごとにより趣きを増しているように感じられた。
そしてなにより心に残ったのが、伝統と最新が見事に混ざり合った世界観が、姿、形は変われども、現在のフライングスパーにも受け継がれているのだと感じたことだ。
そう、ミュルザンヌはひとつの時代の終わりではない。再びひとりで歩き始めたベントレーの過去と未来を繋ぐ“はじまりのクルマ”だったのだ。





2014年に追加されたミュルザンヌ・スピードは、スタンダード比25psアップの537psを発生。また2016イヤー・モデルでマイチェンが施されインフォテイメント・システムが刷新されている。ちなみにミュルザンヌ1台を製造するのに必要な時間はおよそ400時間。そのうち150時間がインテ リアの製作に費されるという。

※『FLYING B No.001』(2022年刊)に掲載された記事に加筆修正しました。掲載された情報は刊行当時のものです。