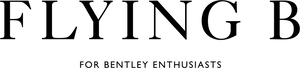BENTLEY DNA -- 1960 Bentley S2 Saloon
静かなるドライビング・ファン、憧憬の小山
90年以上という長い歴史を誇るベントレーのアーカイブには、きら星の如く輝く銘車が名を連ねている。その中において、小山のように盛り上がったボディ、大きく波打つスタイリングをもつ’50年代の末に登場したSタイプもエンスージァストにとって印象深いモデルに違いない。 特に今日まで続くV8エンジンを初めてそのボンネットに収め、ベントレー新時代の扉を開いたS2は、伝統的なシャシーと魅力的な心臓を併せ持った魅力的な1台である。
Text: Takuo Yoshida
Translation: Mako Ayabe and Michael Balderi
Photo: Hidenobu Tanaka
車輌協力:くるま道楽 株式会社ワク井商会
輝く金塊、然るべき1台
ヘッドランプが2灯だったのか4灯だったのかも定かではない。日本がバブル経済の頂に駆け上がろうとしていたある年の冬、まだ免許も取得できない自転車少年だった時分、本牧の街を徘徊していたエンスージァストの私は、ある時小さなレストランの前の路上に駐車していた金色の小山のような自動車に釘付けになった。
ベントレーだ!
まだ空き地も多く、殺伐としていた当時の本牧の枯草色の景色の中にあって、ベントレーSタイプは突如地中から姿を現した金塊のように見えたものだ。リアのガラスこそ真っ黒なフィルムが貼られていたのだが、フロントの窓から中を覗くと、沈んだ臙脂色の内装が見えた。世の中には妙なセンスがあるものだなとその時は思ったが、それでも底知れない凄みのようなものは、十二分に表現されていたように思う。
果たしてどのような乗り心地なのだろうか。それ以上に、どのようなオーナーが乗っているのか見てみたい気持ちも強かったが、今ではずいぶんとモダンになってしまったそのレストランは店内が暗いことでも有名で、見当がつかなかった。当時からひねたクルマ好きだった私は、クルマ自体の格好良さもさることながら、オーナーの身なりが然るべきものでなければ認めないような思いが強かったのだ。
あれから20年以上の時間が経過して、いよいよ明日ベントレーS2のステアリングを握るという晩。私はスタイリストさながらにテーブルの上にツイードのジャケットとモールスキンのパンツを広げ、色の組み合わせを確認して悦に入っていた。旧いクルマはよくドライブしているし、その中にはベントレーも数台含まれているので、過度の緊張はない。けれども、然るべきクルマを試乗する際、俄かオーナーを気取るような時でも身なりは大事だという思いはいまも変わらない。S2はペダルまわりのレイアウトもゆったりとしているはずだから、靴は恰幅のいいチャーチのセミブローグを選んでみることにした。
贅を尽くした出で立ち
暗いガレージからヌッと出てきたベントレーS2は、最初は漆黒に見えたのだが、目が落ち着くと濃紺であることに気が付いた。分厚く巨大で、浜に打ち寄せる大波のような抑揚を持ったボディは、万年筆のように黒いエボナイトの塊から大胆に削り出された芸術作品のように見える。おおよそ鉄板を金型で圧して、溶接で繋ぎ合わせたような印象が希薄なのである。Sタイプを生産していた当時のベントレー・モーターズはラッカー塗料を何十にも塗り重ねていたことで知られているが、それが重厚さの源となっているのだろうか。しかしフロントのバンパーの端から勢いよく立ち上がり、リアバンパーへと波打つように引かれたコーチラインならぬプレスの峰はしっかりと立ち上がっている。
クルマの周囲を見渡せば、生産性を重視したパネルの分割線など一切入っていないことに気づく。ルーフの端で微妙なカーブを描くレインドリップなどは、誰がどのようにして作り上げたというのか? これなどまさに無垢の鉄から削り出されたのではあるまいか。工業製品は往々にして大きなものは大味で、小さなものは繊細に作られているという先入観がはたらいてしまうのだが、ベントレーにその常識は通用しそうにない。とてつもなく大きいのに、隅々まで贅が尽くされているのである。
かつて“金塊”を目の当たりにした時から思い続けているわけではないのだが、いつかはベントレーを所有したいと思っていて、車種はV8エンジンを搭載したスタンダードスティールボディのSタイプに決めている。理由はいろいろとあるのだが、要するに奮発してロンドンのクラリッジスに宿をとったのならば、ディナーはゴードンラムゼイでフルコースをぜひともいただきたい、そういうわけである。
Sタイプはクラシック・ベントレーの中でも人気のあるモデルだが、値段はコーチビルドものに比べればだいぶこなれている。それでもモノコック構造のボディを得てすっきりスマートになってしまったTシリーズよりも威厳に満ちたスタイリングをしている。しかしいくら古いとはいってもテクノロジーは戦後のものだし、かといって複雑にもなっていないので維持費も(こういった天上界の基準においては)リーズナブルらしい。初心者向きなどとはとても言えそうにはないが、ベントレーの魅力を十分に味わえる1台であることは確かだ。そうそう、シリーズ2以降のモデルであれば、エンジンは現代まで続く銘機、オール・アルミニウム製のV8を搭載しているのである。
アンダーステートメント、しかし豊潤
濃紺の小山を前になかなかクロームメッキのドアハンドルに手を掛けられなかったのだが、まずは重厚なリアドアを開けてみた。漂ってくる微かな芳香は、アンティークショップに紛れ込んだような錯覚を覚えさせる。目の前に佇む大きなリアシートは、クルマのそれというよりは、伝統を持つホテルのサロンに置いてあるソファーによく似ている。
いくらツイードのジャケットを羽織り、カントリー・ジェントルマンを気取ってみたところで、実際にシートに腰を沈めてみると、それがリアシートであるにも関わらず、運転手が休憩しているようにしか見えないはずだと悟った。少し頭が白いくらいでないと、人間の方が気圧されてしまうのだ。
シートの表面にふんだんに張られたコノリー・レザーと、中身のアンコにはまだ充分な弾力が残っている。座面の前後長も、フロントシートとの間隔もたっぷりとある。そして背もたれの角度もフロントに比べればはるかに寝ているので、リアシートに座る人物は、例え緊張していたとしても、リラックスした姿勢をとることができるのがこのクルマの特徴といえるだろう。
室内の明るさも絶妙だ。プライバシー・ガラスになっていないにも関わらず、室内に入り込む光はうまい具合に調節されていて、例えばピクニック・テーブルや読んでいる本には光が当たるのだが、パッセンジャーの顔は陰に隠れるので、眩しくない。内側にミラーが仕込まれた太いCピラーがプライバシーをほどよく守ってくれているのである。室内にこれだけゆったりとした空間が確保されているにも関わらず、リアドアのサイズがフロントに対して小さく設えられているあたりに、イギリス人特有のアンダーステートメントを感じることができる。
フロントシートも、シンメトリーに工作されたバーウォールナットのダッシュパネルとコノリー・レザーが張り巡らされた豪奢な世界観がある。驚くべきは、座面の横一杯に使われているレザーが一枚ものであることだろう。ビニールの反物ではあるまいし、やはりこういった革の使い方は、普通の自動車には見られない。これがさらに古いベントレーであれば、座面の全てが1枚革で覆われるといった場合もある。上には上がいるということだ。
フロントシートの座面は一体のベンチシート型だが、シートバックは左右に分割されており、リアのパッセンジャーの邪魔にならない程度に少しだけ角度が変えられるのだが、シートバックの角度が揃っていた方が見た目にも美しい。
ダッシュパネルの中央にささるイグニッションキーを捻ると、スターターモーターが一瞬唸った後、すぐに6.25リッターV8のアイドリングがはじまった。今なお現役を続けているベントレーV8の始祖であり、いよいよ引退の時が迫っているといわれるこのパワーユニットは、ディストリビューターやキャブレターといった現代では耳慣れなくなってしまった補器類で固められているからだろうか、室内に伝わってくる微かな音や振動が、現代のものよりも滋味に溢れている。
始動する瞬間こそボディをひと揺すりしたが、アイドリングが安定した後は静寂が保たれる。ステアリング・コラムの右から映える華奢なシフトレバーを動かすと、重量感のあるサイレント・スポーツカーは、スッと動き出した。
静寂という名の音の中で
オルガン式のスロットルペダルを静かに倒しこむと、ググッと強力なトルクで加速がついていく。レヴカウンターがないので正確な回転数はわからないのだが、だいたい2000r.p.m.あたりでシフトアップしていく。アイドリングのすぐ上あたりからトルクがたっぷりと出ているのでシフトアップの直後にもたつくようなことは皆無だが、シフトの瞬間ギアボックスが機械的に仕事をしている様子が膝のあたりに感じられる。S2は現代のベントレーと同じく安楽なドライビングを許容してくれる。しかし機械が発するメッセージをより生々しく感じとれる点は、クラシックモデルだけに与えられた特徴だと思う。
細身のステアリングはギアボックスのコンディションが良く正確で、アライメントも適正なのでごく普通に直進してくれる。パワーステアリングのアシストはもちろん強めだが、それを上回る車重があるため、結果としてドライバーはタイヤの状態をよく感じとることができる。このため、適正なコーナリングスピードを把握しやすいのだ。 ひと癖あるのはブレーキ・システムで、これは当時のベントレーの特徴でもあるのだが、機械式の倍圧装置を使用しているため、エンジンが高い回転数で回っているとき=スピードが速いときには効きが良く、遅くなってくると効きが弱くなる。つまりゆっくりと走らせ、そして停止する直前が一番効きが悪いのである。しかし、そのお陰で停止する際にパッセンジャーの頭をカックンと揺さぶるような挙動にもなりにくいのだから、これは意図的なものだと考えることもできるだろう。
軽量で精確なシャシーと鋭いレスポンスのエンジンを搭載したスポーツカーのドライビングを“刺激的”と表現するのは容易いことだが、その逆のゆったりとしたフィーリングを刺激的と表するのは難しいように思える。しかし意外なことに、私にとってベントレーS2のドライビングは十二分に刺激的であり、快感以外の何者でもなかったのである。そう思える背景には、私の少年時代の憧憬があって、この出会いを美化しすぎていることも否定できない。しかしクラシックカーに相対するならば、ロマンチストであるに越したことはないのではないだろうか。
今も昔もベントレーを走らせるという行為は、世の中に静寂という名の音があり、絶対的なスピードの中でも充足を得られる、そんな自動車趣味があることを気づかせてくれるのである。
※「フライングB No.002」(2009年刊)に掲載された記事に加筆修正しました。 掲載された情報は、刊行当時のものです。

BENTLEY S2 SALOONとは 現代にも受け継がれるオールアルミV8OHVユニットを初めて搭載した、ベントレーのスタンダードモデル。R-RシルバークラウドIIと共通のボディを持つ、バッジエンジニアリングカーでもあり、1959?1962年の間に1865台が生産された。また少数ではあるが、H.J.マリナー製ドロップヘッドクーペ(15台)や、LWBモデルをベースとしたジェームズ・ヤング製4ドアサルーン(5台)などの、コーチビルダーによるスペシャルも生産されている。

長大なエンジンルームに収まるV8ユニットは現代ベントレーにも受け継がれる銘機である。
アルナージT/R、ブルックランズ、アズールなど現代モデルに搭載されるV8OHVユニット。ロッカーカバーに施されたエナメルペイントと“BENTLEY”のレリーフが美しい。
 1931年からR-R傘下に収まっていたベントレーに、長らく装着されていたシャシープレート。“CONDUIT St.(コンデュイット通り)”は、ベントレー社創業地の地名である。
1931年からR-R傘下に収まっていたベントレーに、長らく装着されていたシャシープレート。“CONDUIT St.(コンデュイット通り)”は、ベントレー社創業地の地名である。
 正統な英国式表記で“Boot”と呼ばれるトランクスペースは、燃料タンクとスペアタイヤをフロア下に備えるため、天地は薄いが、前後長は長大なデザインを生かして十分以上。
正統な英国式表記で“Boot”と呼ばれるトランクスペースは、燃料タンクとスペアタイヤをフロア下に備えるため、天地は薄いが、前後長は長大なデザインを生かして十分以上。
 R-Rシルバークラウドと同じ意匠の集合メーターは、電流計、水温計、燃料計、油温計をひとつに纏めたもの。長らくベントレーの伝統であったレヴカウンターは装備されない。
R-Rシルバークラウドと同じ意匠の集合メーターは、電流計、水温計、燃料計、油温計をひとつに纏めたもの。長らくベントレーの伝統であったレヴカウンターは装備されない。
 後席はソファのようなコノリー・レザー張りシートに、造りの良いピクニックテーブルを備える。ドライバーズカーのS2だが、ショーファードリブンにも十分使える装備を持つ。
後席はソファのようなコノリー・レザー張りシートに、造りの良いピクニックテーブルを備える。ドライバーズカーのS2だが、ショーファードリブンにも十分使える装備を持つ。
 1930~1970年代のT2時代まで、絶えず採用されてきたドアアームレスト。もちろんコノリー・レザー張りで、座高やリーチの長さに合わせて上下調節が可能となっている。
1930~1970年代のT2時代まで、絶えず採用されてきたドアアームレスト。もちろんコノリー・レザー張りで、座高やリーチの長さに合わせて上下調節が可能となっている。
 リアクオーターピラーには、現行のベントレーと同様に、シガーライターが装着された照明付きのバニティミラーを確認できる。灰皿はピクニックテーブル上部に装着される。
リアクオーターピラーには、現行のベントレーと同様に、シガーライターが装着された照明付きのバニティミラーを確認できる。灰皿はピクニックテーブル上部に装着される。
 美しい玉杢が特徴のウォールナットが寄木細工で組み立てられた、なんとも贅沢な内張り。現代ではこれほど目の細かい玉杢を持つ木材は、かなり入手困難になっているという。
美しい玉杢が特徴のウォールナットが寄木細工で組み立てられた、なんとも贅沢な内張り。現代ではこれほど目の細かい玉杢を持つ木材は、かなり入手困難になっているという。
 S2以降は手動変速機が廃止されて4段A/Tのみとなったため、ペダルはA、Bの2つのみ。“B”の刻印が刻まれたブレーキペダルは、現行モデルにも引き継がれる伝統のものだ。
S2以降は手動変速機が廃止されて4段A/Tのみとなったため、ペダルはA、Bの2つのみ。“B”の刻印が刻まれたブレーキペダルは、現行モデルにも引き継がれる伝統のものだ。
 重厚なドアを開けると漂う微かな芳香はアンティークショップに紛れ込んだような錯覚を覚えさせる。
重厚なドアを開けると漂う微かな芳香はアンティークショップに紛れ込んだような錯覚を覚えさせる。
上質なウォールナットベニアのみで構成されたダッシュパネルは、息を呑むほどに端正な造りだ。R-R/ベントレーの伝統に従って、ウッドパネルはすべて中央から左右対称である。
 ドライバーズカーとはいえホールド性よりも快適性を優先したシートは、平板な形状が特徴だ。ドライバーの乗降により座面の右側が擦れているのも年季を感じさてくれる。
ドライバーズカーとはいえホールド性よりも快適性を優先したシートは、平板な形状が特徴だ。ドライバーの乗降により座面の右側が擦れているのも年季を感じさてくれる。
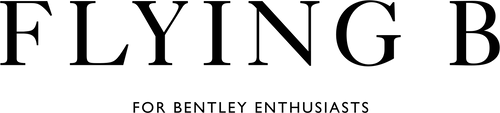


 ベントレーを走らせるという行為は静寂という名の音があることを知ることなのかもしれない。
ベントレーを走らせるという行為は静寂という名の音があることを知ることなのかもしれない。