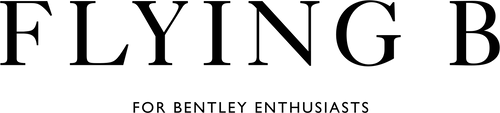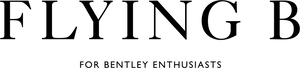BENTLEY CHRONICLE PART1 : #006
BENTLEY CHRONICLE PART1
W.O.ベントレーとベントレー・ボーイズの時代 #006
1929年ル・マンにて。この年からショートカットするかたちに改装されたポンリューヘアピン('32年に完全廃止)を、自身初の勝利に向かってひた走るバーキンの“オールド・ナンバー・ワン”。
■トップ4台を独占し3年連続優勝を果たす
1929年のル・マンは、W.O.ベントレーとベントレー・ボーイズたちにとって、間違いなく史上最高のレースであったに違いない。もはや盟主としての風格さえ漂わせていたベントレー・ワークス・ティームは、前年の覇者バーナートと“ティム”バーキンの乗る最新の6気筒6.6リッターモデル“6 1/2リッター・スピードシックス”に加えて、ジャック・ダンフィー/グレン・キッドストン組、ベンジャーフィールド博士/ド・エアランガー男爵組、クレメント/シャサーヌ組、そしてもう1人の前年の覇者ルービン/ロード・ハウ組からなる4台の4 1/2Litre、つまり総計5台の大体制を組んでエントリーした。この年のライバルは、前年の上位入賞で勢いを得たスタッツ、クライスラーなどのアメリカ勢であった。
この5台のベントレーのうち、ルービン/ハウ組のカーナンバー11のみはわずか7周目で、ダイナモのトラブルでリタイアしてしまうが、残った4台は素晴らしい快走ぶりを見せてレースを圧倒する。特にバーナート/バーキン組のスピードシックスの速さは別次元的なもので、18周目にはバーキンがこの年のファステストラップとなる7分7秒(平均速度137.929km/h)をマーク。結局ゴールまでに2843.830km/hを走破して堂々の総合優勝を得た。しかも2位以降もダンフィー/キッドストン組(マシーンは3年目の“オールド・マザー・ガン”)、ベンジャーフィールド博士/ド・エアランガー男爵組、クレメント/シャサーヌ組の順で3台の4 1/2Litreがフィニッシュ。ベントレー・ワークス・ティームがトップ4を独占してしまうという、まさに王者の称号に相応しい結果となったのである。
■5度目の勝利を得るもワークス・ティームは撤退に
通算4勝の戦果を引っさげてル・マンに乗り込んできたベントレー・ワークス・ティームは、この年3台のスピードシックスをエントリー。まずバーナートは、前年の優勝で“オールド・ナンバー・ワン”と呼ばれることになった愛車スピードシックスで、キッドストンとのコンビで出場。加えてクレメント/リチャード・ワトネィ組、サミー・デーヴィス/クライヴ・ダンフィー(ジャック・ダンフィーの兄)組もワークスのスピードシックスで参戦した。
しかし、この年のル・マンではベントレー・ワークスの前に新たなライバルが現われた。“ティム”バーキンの主導で開発し、裕福な貴族女性ミス・ドロシー・パジェットによってエントリーされたベントレー4 1/2ブロワーである。このマシーンももちろんベントレーが製作したのだが、この時期になるとベントレー社の財政もかなり逼迫していたので、W.O.はワークス体制でのエントリーについては断っていた。そこでバーキンは、パジェット女史から支援を取り付け、バーキン/シャサーヌ組とベンジャーフィールド博士/ジュリオ・ランポーニ組の2台体制で、なんとかル・マン参戦に漕ぎつけたのだ。しかし、バーキンの野望は脆くも崩れることになった。彼は6分48秒の最速ラップタイムをマークする健闘を見せたが、2台の“ブロワーベントレー”のエンジンはともに重大なトラブルを発生。日曜の午後に相次いでリタイアを喫してしまったのである。
しかし、ベントレーの権威は“オールド・ナンバー・ワン”を筆頭とする2台のスピードシックスが守り通した。メルセデスSSに乗るカラッチオラ/ヴェルナー組との10時間に及ぶバトルに打ち勝ったバーナート/キッドストン組は、ベントレーにとって5度目となる優勝を獲得。2位にもクレメント/ワトネィ組が入賞し、W.O.とベントレーボーイズの最後の栄光に華を添えた。バーナートは3回のみ参加したル・マンのすべてで総合優勝、つまり勝率10割という素晴らしい記録を残すことになった。
しかし、栄光の陰で慢性的な経営難に喘ぐベントレー社とバーナート会長は、この年の8月をもってワークス体制でのレース活動から完全撤退するとの決定を下さざるを得なくなってしまったのである。
※「フライングB No.001」(2008年刊)に掲載された記事に加筆修正しました。 掲載された情報は、刊行当時のものです。