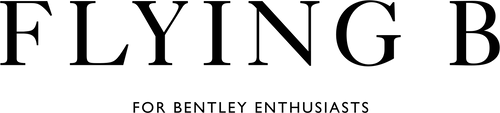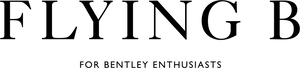BENTLEY DNA
BENTLEY T 2-DOOR SALOON BY JAMES YOUNG
A Realm of Maturity Created by the Bespoke
BENTLEY DNA
BENTLEY T 2-DOOR SALOON BY JAMES YOUNG
ビスポークで生み出された熟成
イギリス人は古いモノを捨てない。イギリス人は古いものを直して使う。だがその背景にあるのは、エコや節約といった理由ではない。人の一生を優に越える本物を作っているからこそ、長年の使用に耐え得るのである。かつて、コーチビルダーと呼ばれるボディ職人が腕を振るっていた時代の最後の名残とも言えるジェームズ・ヤング製のボディを纏うベントレーTは、まさに"これから"という熟成の質感を湛えて、今日もアスファルトの上を滑空している。
text:吉田拓生
photo:田中秀宣

誂えたイギリスの逸品
人間が使う道具の多くは、突き詰めれば必ず誂えの世界へと行き当たる。人はそれぞれ体格が違うわけだし、趣味趣向だって異なるからこれは当然のことといえる。物自体もその起源を辿れば、マスプロダクションが始まるはるか以前からオーダーメイドがあった例がほとんどなのである。かつて7つの海を統治し、世界中から最高の富を逸集していたイギリスの場合、その例が顕著といえる。紳士が身に付けているアイテムを思い浮かべてみてほしい。シャツやハット、そしてテイラーで誂えるスーツなどはその代表格といえる。もちろん、足元を引き締める靴も同じこと。
今日でもサヴィルロウ・ストリートに軒を連ねるテイラーが相当な数にのぼるのに対し、ビスポークの紳士靴を扱うお店は驚くほど少ない。メジャーなものではジャーミンストリートのフォスター&サン、オールドボンドストリートのジョージ・クレバリー、そしてセントジェームスストリートに店を構えるジョン・ロブが有名である。
古式ゆかしい建築物が悠久の時を感じさせてくれるロンドンの街中だが、実際の流れは東京よりもはるかに忙しなく、道路脇にクルマを止めると、ものの1分で駐禁を取られそうになるほどである。ところが以前、不可解な光景に出くわした。エビ茶色の少々風変わりなベントレーがロンドン・ロブの前に堂々と駐車していたのでしばらくそれを眺めていたのだが、これが一向に駐禁をとられる気配がない。中にショーファーを待機させているわけでもないのに、である。おそらくベントレーの主は、ジョン・ロブで新たな一足を"ビスポーク"していたに違いない。さてそのベントレーのどこが風変わりだったかというと、ミュルザンヌやターボRと同じマスクであるにも関わらず、しかしドアが2枚しかなかったのである。つまりこちらもビスポーク、ベントレー流にいうならばコーチビルドされたモデルということになる。何か特別な駐車証でも持っているから駐禁をとられないのだろうか?それともベントレーのオーラが駐禁係を寄せ付けないのか?真実のほどはわからずじまいだが、然るべき人に恥を欠かせないという特殊な文化がイギリスにはあるのではないか、と個人的にはそう思いたいところだ。
高尚さゆえの控え目な意匠
今回"DNA"を飾るオフホワイトのベントレーも、おそらくロンドン・ロブの店の前に堂々と駐車しておける資格があるに違いない。スタンダードスティールボディのベントレーTに酷似したマスクを与えられている2ドアボディという点において、マリナー・パークウォードが手掛けたコーニッシュとの違いがわからないという方がいるかもしれない。だがしかし、リアフェンダー手前でボディサイドのプレスラインが大きくキックアップするコーニッシュのそれとは違い、ジェームズ・ヤング製のボディは、4ドアのスタンダードボディと同様、ヘッドランプ脇からテールランプまで、直線的なラインが彫られていることで違いが際立つ。車体のどこにも見慣れたメッキプレートによるエンブレムは見当たらず、総じて控え目な印象であることから、個人的にはジェームズ・ヤング・ボディの方に好ましい印象を受けた。
このベントレーTの素性は、ドアを開けた時に現れるサイドシルが物語ってくれる。そこにはコーチビルドを手掛けたジェームズ・ヤングのコーチプレートと、このクルマをデリバリーしたチェルトナムのディーラー、ブロウトンズの銘が見て取れるのである。イングランド北西にあるクルー工場で出来上がったベントレーTのローリングシャシーがケント州に運ばれ2ドア・ボディが架装され、そして風光明媚なコッツウィルド地方、チェルトナムで顧客に引き渡される。そんなこのクルマの素敵な背景に敬意を払いつつ、たっぷりとしたドライビングシートに腰を降ろす。
室内の設え、ボンネット上に彫り込まれた抑揚、そこはまさに、見慣れたベントレーTのそれである。コーチビルドもののベントレーがジョン・ロブのようなビスポーク・シューズと違うのは、それがセカンドオーナーの体躯にもフィットする包容力を備えている点かもしれない。そう、クルマはモノとしての寿命が、人の一生よりもはるかに長い場合も少なくないのだからこれも頷ける。
ダッシュ中央に設けられたイグニッションを捻り、6.75L V8エンジンに火を入れる。スターターが起動する一瞬、微かにボディが揺すられるが、その直後から再び無風の湖面のような静寂が室内を満たしてゆく。現実問題として旧いクルマの機関に暖機運転は必須だが、しかしベントレーのそれは少しも退屈ではない。シガーを燻らせる時間にも似た、ある種の充足を乗り手にもたらしてくれるのである。多分に嗜好的な要素を帯びた乗り物を、単なる移動の道具と断じることはできない。それは例えばスウェイン・エドニーのアタッシェや、アルフレッド・ダンヒルのパイプ、コーディングスのカバートコート、ジェームズ・ロックのハット、そしてベントレー......職人が手掛けたイギリス一流の品々は、機能もさることながら、その佇まいや感触、作り込みが醸し出す存在感に最大の特徴があるのだ。
時を越える隔絶感
ステアリング・コラムから伸びる細い枝のようなシフトレバーは、やはり細身のエボナイト製ステアリングを右手で握りながら操作できる位置に生えている。シフトのインジケーターにはR.N.4.3.2という文字が輝いているから、このクルマは4段のオートマティック・トランスミッションを備えていることになる。ブレーキをリリースし、まだ夜の明けない都内へと滑り出す。
ヒストリックカーのコンディションは、走りはじめてものの5分もすればあらかた見えてくる。首都高速に乗ってすぐ、肩の力が自然と抜けていった今回のベントレーTは、間違いなく当たりの個体といえる。これまでドライブしたことのあるTシリーズとの最大の違いは、走らせた時の軽やかさにある。車輌重量が軽いわけではない。エンジンの扱いやオーバーホールの具合が良かったのか、パワートレーンから脚まわりに至るまでのブッシュや軸受けなどの状態が良いのか、はっきりと指摘することはできないのだが、その乗り味には一体感が漲っている。齢40年を越えるようなヒストリックカーの場合、数人のオーナーの元を転々とし、やはり複数のメカニックが手を入れていることが珍しくないがそこで発生したちょっとしたメンテナンスの積み重ねが、個体の性格となって滲み出てくるのだろう。そうだ、今回の撮影は少し遠くまで足を伸ばしてみることにしよう。
現行モデルと過日のベントレーのドライブ・フィールは、他の自動車と同様にずいぶんと異なっている。現行モデルがしっかり感を強調しているとすれば、'50~60年代のモデルは線の細さが先に立つ。ステアリングの細さ、タイヤの細さ、パワーアシストの強さ、これらが安楽なドライブを提供すると共に、乗り手へのフィードバックを希薄にしている。だが、五感を研ぎ澄ませてそのパルスを感じようとすれば、その根底にはやはり骨太でスポーティな本質が込められていることがわかる。オールドモデルをドライブする度に、そんな独自の周波数をキャッチするのに時間がかかってしまうのだが、いったん体が馴染めばクルマが言わんとしていることが明快に見えてくる。まるで誂えたイギリスの靴が、主の体温を感じて然るべき軟らかさを取り戻していくように。
表面的な感触には差があるが、しかし今も昔も、ベントレーのドライブ・フィールに共通する最大の特徴は、隔絶感にあると思う。自分がドライブしているにも関わらず、どこかへ運ばれているような感覚。道路の上を走っているにも関わらず、微かに滑空しているような感覚。それらがベントレーをベントレーたらしめている。ノーズの先端、ラジエーターグリルのトップに輝くフライングBのマスコットが、それ自体魂を持って水先案内しているように思える時があるのはそのためだ。
現行モデルのベントレー・コンチネンタルGTの魅力が、今から40年くらい後の世において失われているとは考え難い。かように、白い小山のように雄々しいベントレーTは、今なお質の高さを控え目に主張しつつ、実際に魅力に満ち溢れている。日頃の整備さえ怠らなければ、毎日のアシとして今日も立派に仕事を成し遂げるに違いない。
そう、イギリスの職人が誂えた道具は、時間を経て古くなるのではなく、熟成しより良い状態へと近づいていく。その点においても、ジェームズ・ヤング製のボディを纏った今回のベントレーTは、少し年季が入って、まさにこれからという時を迎えているのである。
1967BentleyT2-DoorSaloon byJamesYoungとは
1919年の創業から1932年までに生産されたベントレーは、創業者であるW.O.ベントレー自身が開発に関わったこともあり、今なお特別な尊敬を集めている。当時の自動車メーカーはおもにシャシーとエンジンの製作を手掛けており、ボディはコーチビルダーと呼ばれる専門業者が架装していた。今回の取材車、シャシー&エンジンNoHF3195、レジストレーションNoYV1471は元々ヴァンデンプラス製のサルーン・ボディを纏っていたが、後年ル・マン・タイプのファブリック・ボディに換装されたヒストリーを持っている。

細身のステアリングが優雅な風情を醸し出すベントレーTのインテリア。ダッシュパネルのウッド類はリペアを受け完璧なコンディションを誇っている。2ドアとはいえ、サルーンの名の通り、室内はルーミーに設えられており、シートもスタンダード・サルーンに準拠した厚みのあるものが奢られている。

粛々と回るエンジンはおなじみの6.75L V8。4段オートマティックと組み合わされる。そのエンジン・ルームからは現代のクルマらしからぬ複雑さが窺えるが、しかし44年前のクルマとは思えないコンディションであることも確か。キャブレターはSUが2基備わっている。
サイドシルにはコーチビルダーとディーラーのプラークが付き、このクルマの素性を然るべき人に対してのみ主張している。
バルクヘッドに留められた古のベントレー・プラーク。ファクトリーは現在と同じくクルーだが、会社の住所はロンドン、コンデュイット・ストリートになっている。
ドア開口部に留められたコーチビルダー、ジェームズ・ヤングのプラーク。自らの仕事にプライドを持ちつつ、それを控え目に主張する、実にイギリス人らしい所作が感じられる。
2ドアとはいえ、リア・シートにも一切手は抜いていない。充分な足元スペースはもちろんのこと、各々にバニティミラーや灰皿、シガーライターが備わっている。



外観から想像するとおりの広さを誇るリア・トランクスペース。フロア下には燃料タンクとスペアタイヤが収まるが、それでもなお充分な高さが保たれている。


※『フライングB No.005』(2011年刊)に掲載された記事に加筆修正しました。掲載された情報は刊行当時のものです。