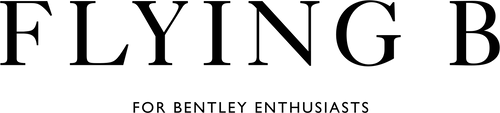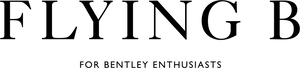HISTORY
1954 Bentley R-Type Continental by H.J. Mulliner
The Benchmark for Modern Bentleys
モダン・ベントレーのベンチマーク
現行コンチネンタルGTのモチーフにもなったRタイプ・コンチネンタル。
ここではその誕生から終焉までの歴史を細かく追っていくことにしたい。
text: 武田公実
photo: ベントレーモーターズ ジャパン
Translation: Mako Ayabe and Michael Balderi

サラブレッドの血統
1952年から約3年にわたり製作されたベントレー“Rタイプ・コンチネンタル”は、スタンダード・スティールサルーン、Rタイプをベースに製作されたスポーティなグランドツアラーだった。中でも、当時のR-R/ベントレーが最も信頼を寄せていたとされるコーチビルダー“H.J.マリナー”が製作したプレーンバッククーペは、1992年にデビューしたパーソナルクーペ“コンチネンタルR”のデザイン上のモチーフとされたことから、誕生以来40年を経て再び脚光を浴びることになった。
しかも2002年にデビューし、ベントレー大躍進の原動力となった大ヒット作、“コンチネンタルGT”では、さらにRタイプ・コンチネンタルに近いプレーンバックスタイルを採用。そのオフィシャルカタログでも、新旧コンチネンタルのプロフィールをシルエットとして上下に並べた写真を掲載することによって、“コンチネンタル”の血統の濃さと正統性を強調している。そして、今年春からデリバリーが始まったばかりの最新型クーペ“ブルックランズ”の公式カタログには、同じRタイプ・コンチネンタルのパークウォード製クーペをモチーフにデザインされた旨が堂々と明言されていた。
つまりRタイプ・コンチネンタルこそ、現代のプレミアムカーマーケットを席巻するベントレー製クーペたちがオマージュとする偉大な存在。“サイレントスポーツカー”という有名な称号を奉られていた時代、そしてロールス・ロイス傘下にあった時代のベントレーの中では、少なくとも現時点においては議論の余地の無い“最高傑作”と称されている。
コンチネンタルの称号
第二次大戦後、名実ともに世界最大の自動車消費地となった北米マーケット。そのアメリカの富裕層が先ずベントレーに求めたのは、自らステアリングを握ってドライブを楽しめるような高級パーソナルサルーンだった。そんなリクエストに応えるかたちで1946年にデビューしたのが、戦後ベントレー初の新型車“マークⅥ”である。その翌年にデビューすることになるロールス・ロイス“シルヴァーレイス”用として開発された新世代シャーシーフレーム(ショート版で127インチ)を120インチに短縮する一方、同じくシルヴァーレイスと同型の直列6気筒Fヘッド(吸気がOHV/排気がサイドバルブ)4257ccのエンジンを、ツインのSUキャブで軽くチューンして搭載したモデルだが、その最大の特徴は、ベントレーとしては初めて、チェシャー州クルーの自社工場にて製作されるスティール製のスタンダードボディを持つことだった。裏を返して言えば、戦前のベントレーはすべてコーチビルダー製のビスポーク・ボディを持つのが伝統的慣例だったのだ。
マークⅥに架装された全鋼製サルーンボディは、第二次大戦の開戦直前に製作された先進的なプロトタイプ“コーニッシュ”をベースに、ベントレー伝統のラジエーターグリルと組み合わせるなど、より現実的なデザインとしたもの。R-Rのイメージが強いコーニッシュは、もとはと言えばベントレーが使用していたネーミングだったのだ。また、マークⅥからはR-R伝統のパルテノン神殿型ラジエーターグリルを組み合わせた姉妹車“ロールス・ロイス・シルヴァードーン”も派生、'49年から同じR-Rクルー工場にて生産されることになった。そして1951年には、6気筒Fヘッドエンジンをボアの拡大によって4566ccまでスケールアップ。翌’52年にはトランクスペースを拡大するなどのマイナーチェンジを受けるとともに、ネーミングも新たに“Rタイプ”に改名されることになった。
マークⅥ/Rタイプは、たしかに当時の高級サルーンとしては高性能かつ魅力的なクルマだった。しかしベントレーと言えば、開祖W.O.ベントレーの時代から、ル・マン24時間で計5勝を果たした真のスポーツカーとして、世界中のエンスージァストの憧れを集めてきた名門中の名門。そして、1931年にロールス・ロイスと合併したのちの“ダービー・ベントレー”時代(“ダービー”はR-Rの旧工場所在地)にも、“サイレントスポーツカー”という象徴的な称号とともに、当時のモータリストから高性能ツアラーとして高い評価を得てきたブランドである。戦後、繁栄を取り戻しつつあった高級車マーケットにおいては、そのベントレーが製作する唯一のモデルがスタンダード・スティールサルーンということが、少々寂しく思われ始めていたのだ。
そこで、戦前のベントレーの栄光を復活させるべくして開発されたのがRタイプ・コンチネンタル。クルーのエンジニア、アイヴァン・エヴァーデンらの提案で1951年初頭に開発プロジェクトが立ち上がった当初は“コーニッシュⅡ”と呼ばれていた。そのパワーユニットは、'51年に排気量を4.5リッターに拡大した後期型マークⅥをベースに、大径のキャブレターの装着や圧縮比のアップ、そして専用のエグゾーストマニフォールドなどのチューンアップを施されていた。そのパワーについては“必要にして充分”としか表記しない当時のR-R/ベントレーの慣習に従って非公表だったのだが、実際にはマークⅥ/Rタイプ・サルーンの約140psから160ps以上までスープアップしていたと推定される。一方、シャーシーは’52年から発売予定のRタイプ・サルーンと共用。つまりマークⅥと大差はなかった。
開発に当たったのはW.A.ロボサムの率いるR-R社開発ティーム。もちろんエヴァーデンは、その主要メンバーだった。'51年8月にはH.J.マリナー製のボディを持つプロトタイプを製作、即座にロードテストに移された。この試作車は、“OLG 490”という登録プレートから、のちに“Olga(オルガ)”の愛称で呼ばれることになるのだが、生産型に移行するに当たって、ルーフを1インチ低めるとともにオルガでは2分割だったウインドスクリーンが一枚の曲面ガラスに改められた。さらに’52年に入ると、R-R社上層部の判断により“コーニッシュⅡ”の車名から、もともとは戦前のR-RファンタムⅡのツーリングモデルに命名されていた“コンチネンタル”に改称された。つまり、結果としてコーニッシュとコンチネンタルの名が逆転してしまったことになる。
そしてRタイプ・コンチネンタルは、Rタイプ・サルーンの発売から先立つこと約4ヶ月、'52年2月から生産が開始されることになったのである。
ベントレー美学の確立
こうして正式デビューを迎えたRタイプ・コンチネンタルは、ベントレーの栄光を取り戻すには充分なモデルであった。エンジンの出力アップに加えて、4段M/Tのファイナルレシオを3.727から3.077に速めたこと、そしてRタイプ・サルーンより約240kgも軽量な上に、空力的なアルミボディとの相乗効果で、英国AUTOCAR誌のロードテストでは、当時としては充分にスポーツカーに入る115.4mph(約185km/h)のマキシマムをマークしたという。このスピードは、当時で言えばジャガーXK120やアストンマーティンDB2のような一流のスポーツカーにも勝るとも劣らないもの。一見したところでは豪奢なプレステージカーながら、Rタイプ・コンチネンタルのパフォーマンスは真のスポーツカー、あるいはグランドツアラーと呼ばれるに相応しいレベルだった。また、'54年にはオートマティックを追加。その直後にはエンジンも4887ccまで拡大された。
'55年までに208台が製作されたとされるRタイプ・コンチネンタルのうち、あとで述べる15台の例外を除いては、H.J.マリナー製の最も有名な、そして最も魅力的と言われる総アルミニウムのプレーンバッククーペが架装された。このクーペボディは、全長5mにもおよぶ堂々たるサイズを誇るが、全身にみなぎる緊張感で実際よりも遥かにコンパクトに見せる一方、グラマラスな優美さにも溢れる、たぐい稀な“美”を実現していた。H.J.マリナーといえば、現代ではベントレーの一部門として存続。最新型ベントレー各モデルに設定されたスペシャルオーダープログラムの名称として、今なおベントレーのスペシャル性を代表するビッグネーム。しかしH.J.マリナーの評価を絶対的なものとしたのも、このRタイプ・コンチネンタルの成功が大きいだろう。ただしこのプレーンバッククーペは、架装こそH.J.マリナーで行われたが、デザインワーク自体はエヴァーデンやジョン・ブラッチリーなど、クルーのエンジニアが行ったという。そのデザインは前述のコーニッシュ試作車や、これも戦前にギリシア人実業家の注文によってフランスのプーラン社が“ダービー・ベントレー”に架装、戦後の’50年にはル・マン24時間レースにて5位入賞を果たした“エンブリコス・クーペ”の影響を大きく受けたとされる。
しかし、'49~'51年にピニンファリーナがマークⅥ/R-Rシルヴァードーンをベースに一品製作した一連のクーペ/カブリオレ・ボディの影響も否めないとする歴史家が多数存在するのも事実である。
一方、前述した“少数の例外”としてはパークウォードが6台、フランスのフラネイが5台、スイスのグラバーが3台、そしてフィアット1100/103TVクーペに似たルーフ形状を持つピニンファリーナ製クーペが1台など、バラエティに富んだボディが製作されている。これら名門コーチビルダーが手掛けたボディは、いずれも手叩きのアルミパネルによるハンドメイドで、インテリアのマテリアルや施されたフィニッシュのレベルも、同時期のスタンダード・サルーンのそれを遥かに上回るものだった。
また、事実上のビスポークであるゆえに、オーダー主の細かい注文に応えてハンドメイドされることから、エクステリア&インテリアの仕立てには自由なコーディネートが可能。厳密に言えば、まったく同じ仕様の車輌は1台として存在しないとまで言われていた。もちろん、新車時の販売価格は当時のRタイプ・サルーン4824ポンドに対して、7608ポンドという高価なものだったが、これらのコーチワークボディを持つRタイプ・コンチネンタルは、'50年代の北米およびヨーロッパの両大陸にて、まさに王者のごとく君臨したのだ。そして、このモデルとともに完全復活を遂げたベントレーの美学は、現代のモデルにも確実に引き継がれているのである。
※「フライングB No.001」(2008年刊)に掲載された記事に加筆修正しました。掲載された情報は、刊行当時のものです。