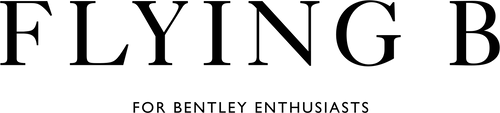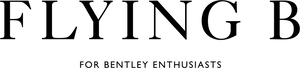BENTLEY DNA
1954 Bentley R-Type Continental by H.J.Mulliner
Magic speed, legendary quality.
魔法のスピード、伝説のクオリティ
セレブリティたちを虜にした、ベントレーの代表作“Rタイプ・コンチネンタル”。
僅か208台だけが生産されたといわれる希少なクーペが、いま目の前に佇んでいる。
長大なノーズ、プレーンバック・テールの伸びやかな曲線、仕立ての良いインテリア。
これほどに美しく、そして勇ましいサルーンをこれまでに見たことがあっただろうか。
きっとその走りも、優れた見た目の印象と完全に符号する、素晴らしいものにちがいない。
text: 吉田拓生
photo: 田中秀宣
Translation: Mako Ayabe and Michael Balderi
車輌協力:くるま道楽 株式会社ワク井商会 phone:03-3811-6170/http://www.bbvideo.jp/kurumadoraku/
取材協力:埼玉スタジアム2002 phone:048-812-2002/http://www.stadium2002.com/

王侯貴族が愛した1台
ベントレーRタイプ・コンチネンタル、このクルマの“格”を的確に捉えた表現はそう簡単に思いつくものではない。ブランド・ネームによっておおよその想像はつくだろうが、おそらくそれだけでは説明が足りていない。ここはひとつ、デリバリーリストに残された著名なファースト・オーナーの名を挙げることで、このクルマの筆舌し難い“格”を感じとってもらうことにしよう。
世界的な海運王として名を馳せたアリストテレス・オナシスはRタイプ・コンチネンタルのオーナーの中でも特に有名なひとりだ。そして彼と親交があったもうひとりの海運王、スタブロー・ニアルコ。ジョン・ロックフェラー2世の三男であり慈善事業家として知られたローレンス・ロックフェラー。フィアットの主でありイタリアを代表するアニエリ財閥のジョバンニ・アニエリ2世もRタイプ・コンチネンタルを注文したひとりである。また、自らの名を冠したレーシングカーまで作ってル・マン24時間レースに果敢に挑戦したアメリカ人実業家、ブリッグス・カニンガムもこの豪奢なクーペの魅力に取りつかれている。その他にもインドやペルシャの国王をはじめとする王侯貴族が我先にと注文を入れた1台、それこそがベントレーRタイプ・コンチネンタルという存在なのである。
このクルマの新車時の価格は、同時代のベーシックカーであるフォード・ポピュラーの約20倍だったという。それを現代のレベルで試算するならば、300万円ほどするフォード・フォーカスの20台分となり、Rタイプ・コンチネンタルの価格は6000万円ほどになると思われる。しかしこのクルマを注文した顧客のほとんどが、気に入りさえすれば値段などいくらでも構わないという人々であることを忘れてはならないだろう。つまり彼らを虜にしてしまうような不思議な魅力を、この2ドア、4シーターのベントレーは秘めていたのである。
そそり立つワインレッドの稜線
総生産台数208台といわれるRタイプ・コンチネンタル、その中の1台が、私の目の前に停まったトランスポーターのアルミ箱の中から、今まさに姿を現そうとしていた。ガルウイング型の屋根が跳ね上がりはじめると、四方八方から差し込んだ朝の光が、Rタイプ・コンチネンタルの上半身で波打つ豊満な稜線を照らしはじめた。最初、そのボディは漆黒に見える。しかしガルウイングが大きく羽を広げると、マルーンともバーガンディともつかない、深みのあるワインレッドであることがわかった。
車体の後ろに回り込むと、左右にテールフィンが立ち上がった特徴的なプレーンバック・テールが伸びやかな曲線を描いている。Rタイプ・コンチネンタルのスタイリングは、'40年代の豪奢なクルマにありがちだった“芸術家が美しさだけを求めて線をひいただけ”のものではないのである。Rタイプ・サルーンのそれよりも3.8cmほど低められたラジエーターグリルから後ろに続く造形は、この時代には珍しい風洞の中でシェイプされた理論的なカーブの集合体なのである。
車体を降ろす段になると、トランスポーターの運転手は事も無げにRタイプ・コンチネンタルのドアを開けて仄かに明るい車内に乗り込んだ。とっさに“エンジンは私が掛けます”と言おうとしたのだがRタイプ・コンチネンタルの特徴的なシフトレバー(それは右ハンドルのドライバーズシートの右脇から生えている)が見えたと思ったら、すぐにドアはドスッという硬質な音を伴なって閉じられてしまった。後には強い嫉妬心のみが残る。これまで試乗したクルマの数は4ケタ近くになるが、こんな気持ちになったのはこれがはじめてだった。
10秒ほどスターターモーターを回しては少し休み、そんな動作が数回続いたが直列6気筒エンジンに火の入る気配はなかった。その場の緊張感がピークに達すると、ようやくコックピットのドライバーと目が合い、交代することになった。コーチビルドを担当したH.J.マリナーの名が刻まれたプレートを跨ぎ、底上げされてフラットになったベントレー特有のフロアに敷き詰められた毛足の長いムートンカーペットを踏みしめ、夢にまで見た1枚革の座面に腰を降ろす。右足でスロットルペダルの具合を確認し、シートの脇に寄り添うように生えるシフトレバーがニュートラルのポジションにあることを確認してから、ダッシュパネル中央にあるスターターボタンを押す。やはり掛かる気配がないので、2度目は1センチほどスロットルを開けた状態で試したがこれもだめ。3度目は意を決して、スロットルペダルをムートンカーペットに深く埋めるようにしながらスターターを回す。すると、シリンダーが1本づつ目覚めはじめ、直列6気筒エンジンは鋭く立ち上がった。それまで渇く一方だった喉が自然と潤うのがわかり、そしてRタイプが私の呼びかけに応えてくれたことを素直に感謝した。
右ハンドル右シフト、至福の時間
直列6気筒エンジンが奏でる低いノイズの中で、至福の時間ははじまった。いつもは退屈きわまりないはずの暖機の時間だが、今日は違う。憧れつづけてきたRタイプ・コンチネンタルのドライバーズシートに、私は座っているのだ。サイズはたっぷりとしているが、しかしRタイプのスタンダード・スティール・サルーンと比べれば遥かにホールド性の良いシートバックに身をまかせ、どの方向を眺めても破綻のない、至高の調度を眺めまわした。
シートやドアの内張りなどに贅沢に張られたきめの細かい革は、今日では自動車用皮革の生産をやめてしまっているコノリー・ブラザースによるアニリン染めである。生成りの革に近いタンの色が、室内を程よい明るさに保ってくれている。ドライバーの眼前には大径のエボナイト製ステアリングが陣取り、その奥には分厚いオールウッドのダッシュパネルが全幅に渡って広がっている。メインの木材は複雑な模様を描く胡桃材(ウォルナット)で、ダッシュを縁取るように象嵌で巡らされた白木は柘植材だ。
外から眺めたRタイプ・コンチネンタルはタイトに引き締まって見える。しかし全長は5.2mもあり、必要にして充分な室内空間も併せ持っている。ひじ掛けの中に葉巻相手でも充分に対応できそうな灰皿を仕込んだリアシートにも一切抜かりがない。
このクルマのチーフエンジニアであるアイヴァン・エヴァーデンは、1950年に設計を開始した時から、“世界最速の2ドア・フル4シーター”を目指していたとされるが、インテリアを眺める限りではその目論見は完全に達成されているといえる。面白いことに今日ではその称号はRタイプの正統な末裔であるコンチネンタルGTスピードのものとなっている。目まぐるしく移り変わる自動車社会の中にあって、RタイプとGTスピードの間には56年もの開きがありながら、しかしその精神は完全なかたちで受け継がれているのだ。なんという血の濃さだろうか。
油温計と水温計の針が立ち上がってきたので、走り出すことにした。まるでサイドブレーキを解除するように少し身をかがめてシフトレバーを操作する。その昔モータージャーナリストは、すばらしいシフト・フィーリングに関して“熱したナイフでバターを切るような”という表現を多用したが、Rタイプ・コンチネンタルのシフトは、フィーリングのみならず、薄くて幅のあるレバーの形状に関しても大きなバターナイフによく似ているのである。
車重が1.7トンほどあるにも関わらず、クラッチミートには少しも神経質なところがなく、スッと行き足がついた。走りはじめてから気付いたのだが、ベントレーのクラッチ・ペダルを踏み込むのは生まれて初めての経験だった。近代のモデルによって、ベントレーといえばオートマティック・トランスミッションというイメージが確立されているが、しかしこのメイクスにそれが初めてオプション設定されたのは'50年代初頭のことなのである。そしてRタイプ・コンチネンタルの右ハンドル右シフトは、'20年代に連続してル・マンを制覇した緑色の祖先たちから連綿と続くスタイルなのだ。
最高の装備とそれを越える走り
Rタイプ・コンチネンタルは、'50年代に誕生した自動車の中でも指折りに高性能な部類に入るが、しかし当時最新の装備だったオートマティック・トランスミッションは'54年になるまで用意されなかったし、レースの世界に登場しようとしていたディスクブレーキはもちろん備えていない。そのかわりにコンベンショナルなマニュアル・トランスミッションやドラム・ブレーキを装備していたのだが、注意しなければならないのは、それらが最高のクオリティを有していたという事実である。
“レンガで出来た便所よりも頑丈な”という表現は、イギリス人がギアボックスへ贈る最大の讃辞であるが、Rタイプ・コンチネンタルのシフトはまさにそれだ。シフトレバーはギアボックス本体から50センチほど離れた場所から生えているのだが、その間は1本の太い鋼棒で結ばれているので、ギア歯の1枚1枚の質量のみならず面取りの確かさまで感じとれるかのような硬質で滑らかなタッチを誇るのである。4887ccの排気量を考えれば、シフトチェンジは忘れた頃に行なえばいい儀式に過ぎないのだが、しかし早くシフトの感触を味わいたいと思えるのだから、これ以上のマニュアルシフトは存在しまい。
ブレーキに関してもギアボックスと同じことがいえる。径の大きなブレーキドラムと適度な粘りを感じさせるシューは、ブレーキペダルのタッチを実に頼もしいものにしており、あらゆる速度域から自信をもってスピードを相殺することができる。絶対的な制動力もさることながら、しばらく乗り続けていてもフィーリングが変化することもない。そしてパッセンジャーの頭を揺らせることなく、静かに停止させるような芸当も得意としているのである。
直列6気筒エンジンのパワーは、ギアボックスがハイギアードに設定されていることもあって、猛烈なものではない。しかしあれよあれよという間にスピードが増していく感覚は軽快であり、他のベントレーとも一味違うし、それ以外の全てのクルマとも決定的に違っている。確かなことは、Rタイプ・コンチネンタルが100km/h以上のハイスピード域を得意としているという点である。最高速が400km/hに到達してしまうような現代のスーパースポーツの悩みは、それに見合う性能を持ったタイヤの存在だが、誕生当時のRタイプ・コンチネンタルの悩みも同じだった。'50年代初頭に最も高性能とされた6層のクロスプライ・タイヤを装着した車重1.7トンのRタイプ・コンチネンタルが120マイル以上の速度で巡航した場合、10分が限度だったといわれているのである。
現代に通じるBのアイコン
ふとステアリングのセンターカバー上にある2つのレバーが気になり見てみると、左はこの時代のクルマには珍しくないハンドスロットルで、右はダンパー(リアのみ)の調整だった。試しにNORMALからHARDにレバーを動かしてみると、想像していたよりもはるかに乗り心地が引き締まるのがわかった。タイヤからのインフォメーションが豊富になると共に、コーナーにおけるロールも明らかに減少した。その走りは、これまで私が想像しつづけてきたRタイプ・コンチネンタルの像とピタリと重なったのである。
'50年代当時にRタイプ・コンチネンタルの雲上の走りを味わった人が、このクルマに惚れ込まない理由などどこにもなかっただろう。Rタイプ・コンチネンタルのプロトタイプをテストした英国AUTOCAR誌のライターが、このクルマを“ドライバーを疲れさせず、どこまでも運んでくれる魔法のじゅうたん”と評した一説は有名であり、それ以上の言葉を探すのは今日でも難しいと思う。しかし、今だからこそ付け加えられることもある。それはRタイプ・コンチネンタルが誕生から半世紀以上が過ぎてなお、世界最高の自動車の1台として数えられている、という事実である。
※「フライングB No.001」(2008年刊)に掲載された記事に加筆修正しました。
掲載された情報は、刊行当時のものです。


長大な4.9リッター直列6気筒エンジンのパワーは例によって非公表とされたが、キャブレターの径などによって、基本になったRタイプのものよりもパワーアップされていた。

直列6気筒エンジンは吸気がOHV、排気はサイドバルブから行なわれる特徴的なFヘッドを搭載していた。その回転フィールは4.9リッターという排気量を感じさせない鋭さがある。

ラダーフレームの上に架装されたボディにはコーチビルダーのプラークが留められている。多くの腕利き職人を抱えていたH.J.マリナーはかつて、ロンドンのチズウィックにあった。

こちらはベントレーモーターズのプラーク。BCからはじまる車体番号がRタイプ・コンチネンタルを表す。コンデュイットSTは、現在ブランド店が建ち並ぶ賑やかな通りだ。

フラットで底上げされたフロアはフレームを持っていた時代のベントレーの特徴といえるだろう。踝まで埋まると評されたムートンカーペットがクルマの車格をよく表している。

見事な模様が入ったウォルナットのベニア。メーター類が奥まって配置されていることからその分厚さがよくわかる。ダッシュを縁取る白い柘植材は象嵌細工で埋め込まれている。

ダッシュ中央の丸いスイッチパネル。左上の銀色のボタンがスターター・スイッチである。ダッシュの中心の模様でウォルナット・パネルが左右対称に配されていることがわかる。

熱を加えて硬化するエボナイト樹脂で成型されたステアリング。その中央部にはホーンボタンの他に2つのレバーが配される。右がリア・ショックの硬さを調整するレバーだ。

分厚いカーペットの穴から顔を出す床生え式のABCペダル。Bの文字が型取られたクラッチとブレーキペダルはけっこうな反力を返してくるが、タッチは正確で、扱いやすい。

低く下がるテール形状のため、トランクスペースは限られている。しかし、誰もが美しいテール形状の前に言葉を失ってしまうだろう。スプリング入りの小さなヒンジにも注目。

ドライバーズシートの右側から生えるナイフのような形状に見えるシフトレバー。乗り降りを妨げないために低められているが、その操作感は非常に硬質で自信をもって操れる。

豪奢な、という表現がピッタリくる内装。シートに使われている革は、面積の広い1枚革が用いられている。ドライバーズシートはシフトレバーを避けるために角が削られている。

コノリーレザーで被われた室内。リアの脚元にもその名に恥じない充分なスペースがある。フロントシートは、シートバックが薄く湾曲したスポーティなタイプも選ぶことができた。

サルーンよりも3.8cm低められたラジエーターグリルの上に輝くフライングBのエンブレム。右側の立体的なタイプは、かつてのラジエーター・キャップの名残である。
SPECIFICATIONS
1954 Bentley R-Type
Continental by H.J.Mulliner
Dimensions
Length: 5254mm
Width:1816mm
Height:1670mm
Wheelbase: 3048mm
Track Width Front:1435mm
Track Width Rear:1486mm
Dry Weight:1625kg
Engine
4887cc F-head 6Cylinders
Horsepower:——
Torque:——
Bore:92.0mm
Stroke:114.3mm
Compression Ratio:7.0:1
Transmission
4-Speed Manual+Reverse
Ratios
1st:2.670
2nd:1.540
3rd:1.210
4th:direct
Final drive Ratio:3.077
Suspension
Front:Double Wishbone + Coil spring
Rear:Rigid axle + Leaf spring
Brakes
Front:Drum
Rear:Drum
Tire
Front:6.50×16
Rear:6.50×16